更新日:
あなたは

番目の訪問者です
(ogino作成共通カウント)
★
旅と歴史ホームページ
OGIさんのHP
信州上田ホームページ
信州長野ホームページ
真田一族のホームページ
Mr.ogino旅ホームページ
上田の旅と歴史HP
信州の旅HP
日本の旅
世界の旅HP
★
|
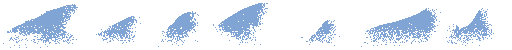
倉敷
 |
倉敷は古代は吉備国と呼ばれ、農耕文化を基盤とし、高瀬舟に積まれた備中米、綿などの集散地でした。慶長19年(1614)大阪冬の陣の際、備中松山藩の代官で倉敷の統治も兼任していた小堀遠州が徳川側に大量の兵糧米を送りました。 |
| 北口アンデルセン広場 |
| その功績が認められたこともあり、寛永19年(1642)倉敷は江戸幕府直轄の天領となったのです。小堀遠州は仙洞御所をはじめ全国に名園を造った人としても有名な人です。 |
 |
| 倉敷駅南口 |
 |
延享3年(1746)代官陣屋が置かれると 江戸や大坂に繋がる物資の一大集散地としてより繁栄しました。新田開発で農地が増加し、綿花の栽培で商工業が発展、倉敷川の水路を利用して綿花・米穀・肥料などを取り扱う問屋の倉庫が次々と建てられたのです。 |
| 明治時代になると 豪商・大原孝四郎氏により倉敷紡績所が設立され、その二代目社長の大原孫三郎が大原美術館などを創設しました。 倉敷紡績、クラレとともに倉敷アイビースクエアーなど今日の倉敷の経済、文化、風景を形作る基礎を造り上げました。 |
 |
 |
デンマークコペンハーゲン市庁舎のシンボル塔を模して設置された時計塔です。からくり時計になっていて決められた時間に人形が出てきます。4人のバイキング像が緑の中で広場を見守っています。 |
| 明治24年(1891)に開業した倉敷駅です。水島臨海鉄道との乗換駅でもあり、南口は繁華街で、路線バスのターミナルにもなっています。北側はアンデルセン広場、チボリ公園になっています。 |
 |
倉敷チボリ公園
くらしきちぼりこうえん
倉敷市寿町12
 |
JR倉敷駅の北側には、平成9年(1997)にテーマパーク「倉敷チボリ公園」がオープンしました。160年の歴史を誇るデンマークの「チボリ公園」をモデルにしています。 |
| この公園はアンデルセンの童話の世界とヨーロッパの古い町並みを再現しています。アンデルセンはデンマークの「チボリ公園」で童話の構想を練ったそうです。 |
 |

 |
公園の広さは、岡山後楽園とほぼ同じ位の大きさだということです。チボリ湖にある小島「人魚の島」には人魚姫像があります。この公園のテーマは「ハートフル」あらゆる年代の人々を受け入れています。 |

| コペンハーゲンの古い町並みを再現した「オールドコペンハーゲン」、コロニーガーデン、バックアレーなど北欧の雰囲気を出しています。 |
 |
 |
花が咲き乱れるガーデンや鳥が遊ぶ大きな池など、見所いっぱいの公園です。イベント・アトラクションも豊富です。 |
| 夜になると「アンデルセンホール」や「チボリタワー」をはじめ、園内では8万個のイルミネーションが輝きます。 |
 |
倉敷アイビースクエア
くらしきあいびーすくえあ
倉敷市本町7−2
 |
倉敷美観地区の東隣にあるアイビースクエアは、明治22年(1889)に建てられた倉敷紡績発祥の工場跡地を利用したスポットです。蔦(アイビー)の絡まるレンガ造りの建物が印象的です。 |
| ホテルを中心に工房、レストラン、チャペル、オルゴールショップ、倉紡記念館、児島虎次郎記念館など多彩な施設で構成されています。 |
 |
代官所跡
 |
アイビースクエア内にある江戸幕府天領倉敷代官所跡です。今も残る堀割と井戸が面影を僅かに残しています。 |
| 浅尾騒動の舞台となりました。中島屋大橋家の分家の敬之助が下津井屋事件で代官の櫻井を恨み周防第2奇兵隊の百人ほどの隊員を引き連れてこの代官所を襲ったのです。 |
 |
大原美術館 児島虎次郎記念館
こじまとらじろうきねんかん
 |
美観地区にある大原美術館の分館です。倉敷アイビースクエア内にあり、明治時代に建てられた倉庫を利用しています。 |
| 児島虎次郎室では大原美術館の作品収集をした「児島虎次郎」の作品と時系列で並べて展示しています。オリエント室では虎次郎が集めた古代エジプトの美術品を展示しています。 |
 |
倉紡記念館
くらぼうきねんかん
岡山県倉敷市本町7-1
 |
明治21年(1888)倉敷で創業した倉敷紡績株式会社の創立80周年記念事業として、昭和44年(1969)に建設されました。土蔵造りの原錦倉庫を当時のままの姿で利用しています。 |
| 当時使用された機械が展示されクラボウの歩みが写真・模型・文書・絵画などによって紹介されています。 |
 |
倉敷紡績発祥工場跡
 |
ほとんどレンガが見えないくらい蔦で覆われた建物です。アイビー学館の中では西洋絵画の流れや様式を分かり易く説明して紹介しています。 |
| 明治の創業期に建てられた工場は、その後現在の倉敷アイビースクエアとなり、当時の原綿倉庫が倉敷の町並みに合わせて改造され記念館に生まれ変わりました。 |
 |
 |
「休養と教養を」というコンセプトで作られたアイビースクエア内のホテルの館内は少し照明を落とした、落ち着いた雰囲気になっています。 |
| アイビースクエア中央広場です。誰でも自由に立ち寄れる広場で、たまにコンサートなども行なわれるそうです。 |
 |
大原美術館
おおはらびじゅつかん
岡山県倉敷市中央1−1−15
 |
倉敷を基盤に活躍した実業家の大原孫三郎が友人でもあった画家の児島虎次郎を記念して昭和5年(1930)に開館した日本で最初の私立西洋美術館です。 |
| 昭和4年(1929)児島虎次郎が他界してしまいました。大いに悲しんだ大原は、児島の功績を記念する意味をもって、その翌年に大原美術館を開館したそうです。 |
 |
 |
ギリシャ神殿風の建物が特徴の大原美術館の本館は創立当初からの最も古い建物です。入り口にはロダンの「洗礼者ヨハネ」「カレーの市民〈ジャン・ダール〉」が待っていてくれます。 |
| 本館、分館、棟方志功室などのある工芸館、中国古美術を集めた東洋館からなっています。有名な巨匠の名画や彫刻や西洋や日本の近現代美術、東洋、オリエントの古美術など、約3000点の幅広い作品を収蔵しているそうです。 |
 |
 |
大原美術館の代名詞のようになっているエル・グレコの「受胎告知」は大正11年(1922)3回目の渡欧中だった児島がパリの画廊で偶然見出して購入したものだそうです。 |
| モネの「睡蓮」は晩年の画家本人から児島が直接購入したといわれています。マティスの「画家の娘」も画家本人が気に入って長らく手元に置いていた作品を無理に譲ってもらったものだといわれています。 |
 |
 |
ニューヨーク近代美術館が昭和4年(1929)に開館しましたが、昭和初期の日本には美術館というもの自体が知られていない時でした。倉敷という一地方都市に美術館を開館したこと自体驚かされます。 |
| 第二次世界大戦の時にここが爆撃されなかったのはこの美術館があったからだともいわれているのです。 |
 |
 |
大原美術館本館と大原美術館分館の間には新渓園があり、近江八景を模して造られた庭も見事です。 |
大原美術館分館
おおはらびじゅつかんぶんかん
岡山県倉敷市中央1-1-15
| 大原美術館の分館です。前庭にあたるスペースには瀬戸内海をイメージしたモダンアートが並んでいます。ロダン、ムーアにイサム・ノグチなどの作品もあります。 |
 |
 |
岸田劉生[きしだりゅうせい]の『童女舞姿』、梅原龍三郎の『紫禁城』をはじめ、萬鉄五郎、青木繁、藤島武二といった近代日本の洋画を展示しています。 |
| 高村光太郎、萩原守衛などの彫刻もあります。地下には現代美術も展示されています。 |
 |
新渓園
 |
かつて大原孫三郎氏の別邸で澆花園と呼ばれていたそうです。大正11年(1922)当時の倉敷町に寄贈され、大原家先代の雅号から新渓園と命名されました。 |
| また孫三郎氏の雅号「敬堂」から敬倹堂と名付けられていた建物は当時公民館として使われていたそうです。平成3年(1991)大原美術館の増築に伴い庭園整備と共に敬倹堂等の建物は一部を解体、保存修復を行ないました。 |
 |
倉敷美観地区
岡山県倉敷市中央1
 |
倉敷市の美観地区は、白壁と堀割の町並み、倉敷川の両岸に柳並木の続く趣豊かな町として全国に知られています。掘割に浮かぶ小舟や揺らぐ川面、悠々と泳ぐ鯉、懐かしい風景がここにはあるのです。 |
| 倉敷は備中松山城の玄関港として、備中国内の天領から米や物資が集積して発展した町です。町割りは江戸時代の名残をとどめています。 |
 |
 |
倉敷川沿いに土蔵が並ぶ一帯は昭和20年代から町並みの保存と修復が唱えられた町並み保存の先駆的な場所です。 |
| 国の重要伝統的建造物群保存地区に選定され、倉敷美観地区と呼ばれています。川沿いに柳並木が続き、なまこ壁の土蔵群や本瓦葺きの町家が並ぶ観光の中心地となっています。 |
 |
 |
倉敷で商いをつかさどっていたのは村役人や地主といった土地の権力者で「古禄 (ころく)商人」と呼ばれる人々でした。政・財を掌握し、富と繁栄を謳歌していました。 |
| 江戸時代半ばを過ぎ、これに対抗する新たな勢力が台頭してきます。綿や干鰯(ほしか)の仲買で財をなし、倉敷に移住してきた「新禄(しんろく)商人」です。 |
 |
 |
新禄派と古禄派はしばしば衝突し、寛政2年(1790)訴訟になり、新禄派が勝ちました。村役人の罷免と選挙制の導入を果たし、農村部の地位向上に大きく貢献したのです。 |
| 現在美観地区に並ぶ蔵屋敷のほとんどは新禄派の家です。大原家の祖先「児島屋」もまた新禄派の商人だったのです。 |
 |
 |
柳並木と中橋です。中橋は明治10年建造で橋桁が一枚石の太鼓橋です。 |
| 旧大原邸の有隣荘です。昭和3年(1928)の建築物で、昭和天皇の倉敷訪問を記念して建てられた大原家の別邸です。大阪の泉州谷川の窯で、緑色に光って見える特別な製法で焼かれた瓦を葺いていることから「緑御殿」と呼ばれていたそうです。 |
 |
倉敷考古館
くらしきこうこかん
岡山県倉敷市中央1-3-13
 |
倉敷考古館は昭和25年(1950)に開館した博物館です。美観地区の中心の倉敷川にかかる中橋のたもとに建っています。約200年あまり前、江戸時代後期の建物で、土蔵づくりの米倉を使用しています。現在残っている蔵造り街並みの中で最も古い建物の一つだそうです。 |
| 下津井屋事件といって下津井屋が全焼して、小山家土蔵(いまの考古館)の前の川に下津井屋親子の首が浮かんだ場所でもあるのです。 |
 |
 |
大橋平右衛門の長女慶の婿養子となった敬之助は米の横流しで下津井屋の若主人を訴えました。江戸から下ってきた櫻井代官が賄賂をもらって入牢していた若主人を釈放したことで事件が起きたのでした。 |
| 考古館の前を流れる倉敷川は、昔は児島湾から瀬戸内海へ通じる運河として船が行きかう重要な交通路だったのです。 |
 |
倉敷民芸館
くらしきみんげいかん
倉敷市中央1−4−11
 |
昭和23年東京の日本民芸館に次いで設けられた日本有数の民芸館です。倉敷の代表的な米倉であった4棟の米蔵を再利用しています。 |
| 白壁の腰に黒っぽい貼り瓦が貼り巡らせてある建物自体がひとつの民芸品になっています。倉敷らしい懐古的な情緒があります。 |
 |
 |
内部は、すべてシンプルで味のある 暮らしに根付いた実用的な民芸品の展示になっています。 |
| 焼物をはじめ木工品、竹細工、漆器、皮革製品、茶壷、織染物、和紙など名もない民衆が作り出したものです。 |
 |
日本郷土玩具館
にほんきょうどがんぐかん
倉敷市中央1−4−16
 |
江戸時代の母屋と蔵を利用した建物です。地元の玩具研究者の大賀政章氏が昭和43年に開いた資料館です。 |
| 倉敷を中心として日本各地の面、人形、凧や江戸から昭和にかけての郷土玩具や雛人形、こまなども展示しています。 |
 |
 |
海外からの収集品もあり合わせると7000点にも及ぶそうです。 |
倉敷館
くらしきかん
岡山県倉敷市中央1-4-8
| 文化庁の登録有形文化財に指定されている観光案内所です。大正5年(1916)に建てられました。中橋の所で川はくの字に曲がる、丁度その前にある木造洋館です。無料休憩所にもなっています。昔は倉敷町役場だったそうです。 |
 |
加計美術館
かけびじゅつかん
岡山県倉敷市中央1−4−7
 |
平成14年(2002)、倉敷市美観地区にオープンした新しい美術館です。加計学園と高梁学園が運営しています。 |
大橋家住宅
おおはしけじゅうたく
岡山県倉敷市阿知3-21-31
| 旧大原邸同様に国の重要文化財に指定されている大橋家住宅は、寛政8年(1796)に建てられた長屋門の住宅です。大橋家は江戸後期の倉敷において,塩田・新田開発によって財をなした大地主で,大原家と共に「新禄」と呼ばれる新興勢力を形成していました。 |
 |
 |
元々大橋家は豊臣氏に仕える武士であったが、豊臣氏滅亡後、京都五条大橋のわきに隠れ住みんでいたので「大橋」氏を称するようになったといわれています。 |
| 下津井屋事件や浅尾騒動の張本人敬之助は大橋平右衛門の長女慶の婿養子でした。代官の櫻井を恨み代官所を襲ったのでした。 |
 |
井上家住宅
いのうえけじゅうたく
倉敷市本町1ー40
 |
本町通りは倉敷のなかでも昔ながらの雰囲気が色濃く残る町です。この町沿いにある井上家住宅は平成14年、国の重要文化財に指定されました。 |
| 井上家住宅は、倉敷に現存する町家としては最古のものとされています。古禄でもある宮崎屋という屋号を持つ旧倉敷村の商家でした。 |
 |
 |
母屋の建物は宝暦3年(1753)に改造されていますが、6代目当主が正徳年間(1711-1716)に建てたものと推定されているそうです。 |
| 南面2階にある7つの倉敷窓すべてに土扉が付いているのが大きな特徴です。 |
 |
中国銀行本町支店
ちゅうごくぎんこうほんまちしてん
岡山市本町2−5
 |
大正8年(1919)倉敷銀行の頭取であった大原孫三郎は地方銀行との合併吸収を続け、倉敷の中心地であった本町通に、第一合同銀行と名前を改め本店改築を行ないました。正面に6本、側面に3本の付柱とドーム型のステンドグラス窓を持つルネサンス様式の建築です。 |
倉敷市立自然史博物館
くらしきしりつしぜんしはくぶつかん
岡山県倉敷市中央2ー6ー1
| 瀬戸内海や岡山県の地史、昆虫、植物と4つのテーマで構成され、人と自然との関わりなどを紹介しています。 |
 |
 |
入口には大昔、瀬戸内海が陸地だった頃 、生息していたナウマンゾウの親子が歓迎してくれます。 |
| 瀬戸内海の成り立ちや古代の生き物と人類の暮らしなどが学べます。 |
 |
倉敷市立美術館
くらしきしりつみじゅつかん
岡山県倉敷市中央2-6-1
 |
倉敷市立自然史博物館の隣にある建物で旧市庁舎本館だった建物を再利用しています。美観地区の近くにあり、建築家・丹下健三氏の設計により昭和35年(1960)に建てられています。 |
| 倉敷市を代表する画家で文化勲章を受賞した日本画家・池田遙邨(ようそん)からの寄贈作品や郷土作家を中心とした作品の収集や展示をしています。 |
 |
総社宮
そうじゃぐう
岡山県総社市2-18-1
 |
総社市のほぼ中心部に、現在の地名の由来にもなっている総社宮があります。大化年間の創建で、備中国の総社です。律令制のもと、国司が国内の神社を巡拝するのを簡略化するために、1ヶ所に祭神を集めさせました。平安時代末期にはほとんどの国に設けられていたようです。 |
| 社殿には備中国内の大小の神祇、つまり延喜式に掲載されている神社、官社が18社、田社(国司の神名帳記載の神社)286社、合わせて304社の神祇を奉斎しているそうです。 |
 |
 |
10月の例祭には、この304社の外に相殿八柱神と末社12社を合わせて324の神饌を奉納する古例が存続しているそうです。 |
| 本殿は昭和55年(1980)に再建されましたが、それ以外の建物はすべて江戸時代に再建されたものだそうです。 |
 |
 |
境内の古代三島式庭園は本殿をめぐる美しい回廊と調和しています。この庭園は平安時代の様式も残しています。 |
| 枝を広げた老木松が池とあいまって神社らしい神秘さと長い歳月を経たものにしかない深遠な趣を見せています。 |
 |
 |
総社は、仁徳天皇(313ー399)の皇妃八田皇女の御名代の地にちなむ八田部(八部)に始まりました。大化の改新(645)によって、吉備国が備前(和銅6年美作国が分かれてできました)、備中、備後の三ヶ国に分かれました。 |
| 備中国の国府が総社市金井戸に置かれ、国司が中心となって祭政一致の政治が行われ、総社宮が造られ、門前町として発展して商品流通の中心地にもなったのでした。 |
 |
 |
戦国時代頃になってから、総社を総社宮とか総社大明神と呼ぶようになり、社の総社が地名として呼ばれるようになっていったそうです。八田部村から総社村となったそうです。 |
| 境内には拝殿から伸びる長く美しい回廊が続いています。また、総社宮は円山応挙をはじめ有名な画家の絵馬を多数所蔵しているそうです。 |
 |
 |
天ノ岩戸を開いた神を祀っています。天照大御神、天ノ児屋根命、天ノ太玉命、思兼命、手力男命、天ノ細女命などです。 |
| 備中の神を祀っています。大国主命、稲脊脛命、事代主命、武御名方命、武甕槌命、経津主命などです。 |
 |
 |
明治29年(1896)総社町となり、昭和29年(1954)合併促進法で近郷の村々と合併して総社市となったそうです。平成17(2005)年都窪郡山手村、清音村とも合併しています。 |
まちかど郷土館
まちかどきょうどかん
岡山県総社市2
| 八角形の楼閣風の入り口が目立ちます。明治のモダンな雰囲気をそのまま漂わせる建物がまちかど郷土館です。 |
 |
 |
明治43年(1910)に建築された旧総社警察署だった建物だそうです。総社市には唯一現存する明治の洋風建築です。明治時代を中心とした地元の伝統産業などの資料を展示しています。備中売薬、阿曽の鋳物、イグサなどの資料が充実しています。 |
井山宝福寺
いやまほうふくじ
岡山県総社市井尻野1968
| 井山宝福寺は、臨済宗東福寺派の中本山で七堂伽藍が揃っている地方では珍しい巨刹です。 |
 |
 |
地元真壁郷出身の名僧・鈍庵(どんあん)が貞永元年(1232)に七堂伽藍を整備してから護国禅寺として繁栄したそうです。 |
| 寺領3千石、末寺の数は300、山内の塔頭子院は55宇という中国地方屈指の大禅林となったそうです。 |
 |
 |
天正3年(1575)備中の兵乱にあい、堂のほとんどが灰燼に帰してしまいました。それでも三重塔と般若院は形骸をとどめることができたのです。 |
| 山門をくぐると、掃き清められた石畳をはさんで、一対の大杉がまっすぐに伸びています、その正面に、仏殿があります。 |
 |
| 仏殿 |
 |
漆喰の壁に丸い窓が印象的な仏殿です。法堂(はっとう)といわれています。本尊の虚空蔵菩薩を安置しています。 |
| 仏殿は重層入母屋造のどっしりとした建物です。中の天井には鰲山筆と伝えられる「水呑の龍」の絵が描かれています。夜ごと絵から抜け出しては仏殿前の白蓮池の水を呑むと恐れられていたそうです。 |
 |
 |
虚空蔵菩薩は300年前この辺の豪族であった薬師寺次郎ヱ門が「力乞い」のため刻んだと伝えられる霊験あらたかなる仏像だそうです。 |
| 井山宝福寺の中で一番大きい建物である方丈です。東西25m、南北16mあるそうです。およそ230年前の建築だそうです。 |
 |
| 方丈 |
 |
方丈の前には幼い雪舟の像があります。水墨画の巨匠・雪舟が少年時代にここで修行したといわれています。雪舟は応永27年(1420)現在の総社市で生まれたそうです。 |
| 絵の好きだった雪舟は修行中に絵ばかり描いて、いつも叱られていたそうです。腹に据えかねた住職が雪舟をこらしめようと 「方丈」の柱に、彼を縛り付けたそうです。 |
 |
 |
住職が様子を見に入ってみると、縛られた雪舟の足元に一匹のねずみがいて足に噛みつこうとしていました。よくよく見ると雪舟が流した涙で足先で描いたねずみの絵だったのです。 |
| 住職は画才を認め、そののち当時の日本の水墨画を代表する画家、周文のいる京都相国寺に修行に入り不動の名声を手に入れたのでした。 |
 |
| 庫裏 |

 |
天正3年(1575)備中の兵乱の際、方丈は焼失し、雪舟が縛られたという柱は現存していません。その後、二度にわたって復興したものが現在の方丈です。 |
| ここの梵鐘は熊山霊山の梵鐘だったそうです。天正10年(1582)の高松城攻めの頃、羽柴秀吉は備中、備前のすべての寺院から鐘を徴発したそうです。あとで返されたときに別の熊山霊山の鐘が戻ったということです。 |
 |
| 鐘楼 |
 |
井山宝福寺の三重塔はおよそ600年前の室町中期の建物といわれ室町中期の特色を有する代表的建造物です。昭和2年には国宝だったそうです。現在は国の重要文化財に指定されています。 |
| 三重塔 |
| 弘長2年(1262)時の鎌倉幕府の執権北条時頼が建立したと伝えられてきました。昭和44年(1969)解体修理が行なわれ、外見上は最新の建造物となりました。 |
 |
 |
この解体修理の際に発見された墨書銘から永和2年(1376)の建立であると判明しました。塔内一層には須弥壇を設け、大日如来と脇侍四天王を安置し天井には約250年前の人で号山和尚筆の天女の絵があるそうです。 |
| 仏殿裏にある古い井戸です。鈍庵和尚が四條天皇の病気全快を祈って懸祈懸祷をすること七日のとき、大音響とともに流星が落ちてきたそうです。それと同時に天皇の病いは平癒されたそうです。 |
 |
| 千尺井 |
 |
落星の地に井戸を掘り「千尺井」と名付けたそうです。「井山」という山号はこれより名付けられたそうです。 |
作山古墳
さくざんこふん
岡山県総社市三須
| 県立自然公園、吉備路風土記の丘に含まれる史跡のひとつです。隆盛を誇った吉備国の象徴です。岡山県下では造山古墳に次いで2番目の規模です。 |
 |
 |
自然の丘陵を利用して造られた全長286m、高さ24mの前方後円墳で、全国で9番目の規模だそうです。 |
| 埋葬者は不明ですが、3段構造になっていることから、吉備地方を支配していた権力者の墓であったようです。 |
 |
備中国分寺
びっちゅうこくぶんじ
岡山県総社市上林1046
 |
備中国分寺は奈良時代に全国に建てられた国分寺のひとつです。市南部のアカマツにつつまれた丘陵地のほぼ中心部に建っています。 |
| 建物は南北朝時代に焼失したと伝えられ、現在の建物は江戸時代中期以降に再建されました。日照山国分寺は備中国分寺跡に、江戸時代中期に再建された真言宗の寺院なのです。 |
 |
 |
五重塔は江戸時代後期、文政4年(1821)から20数年をかけて建立されたもので県下唯一の五重塔です。高さ34.315m。方三間本瓦葺き、3層目までは総ケヤキ造りで、4、5層は松材造りです。 |
| この五重塔は、 屋根の上層と下層がほぼ同じ大きさの細長い造りで相輪も短く、江戸時代後期の様式を濃く残す代表的な塔です。 国の重要文化財に指定されています。 |
 |
 |
塔内は初重内部中央に心柱が立ち、四周に四天柱を据え、その内側に仏壇を作り、四如来像を安置しています。 |
| 天井は格子状で天井板には55cm角大の欅の一枚板を使い、彩色画が描かれ、堂内をいっそう荘厳にしています。 |
 |

 |
絵は全部で104枚あり、四天柱の脇にある4枚の天女図のほかは 季節の花々を描いた草花文です。 |

| 備中国分寺跡は国指定史跡になっています。吉備路のシンボルともいえる史跡で吉備平野の自然と調和し、四季折々表情を変えて美しい姿を見せてくれます。 |
 |
備中国分尼寺跡
びっちゅうこくぶんにじあと
岡山県総社市上林
 |
備中国分寺とともに建立された官寺の遺構です。推定で東西約108m、南北216mの寺域が確認されています。ここは金堂跡です。直径約70cmの円形の柱座や地覆座をもつ大形の礎石がほぼ当初の位置に現存しています。 |
 旅と歴史のホームページへもどる 旅と歴史のホームページへもどる  日本のページへもどる 日本のページへもどる
|
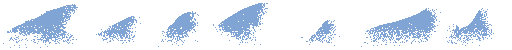
 旅と歴史のホームページへもどる
旅と歴史のホームページへもどる  日本のページへもどる
日本のページへもどる