更新日:
あなたは

番目の訪問者です
(ogino作成共通カウント)
★
旅と歴史ホームページ
OGIさんのHP
信州上田ホームページ
信州長野ホームページ
真田一族のホームページ
Mr.ogino旅ホームページ
上田の旅と歴史HP
信州の旅HP
日本の旅
世界の旅HP
★
|
萩城址
はぎじょうし
山口県萩市堀内

 |
萩城は毛利輝元が慶長9年(1604)に築城に着手し、4年後の同13年(1608)に完成させた平山城です。指月城(しづきじょう)よばれ、城跡は国の史跡に指定されています。 |
| 慶長5年(1600)、西軍の総大将であった輝元は関ヶ原の戦いに敗れ自国に逃げ帰りました。その結果中国地方8ヶ国の領地を削られ120万5千石から、周防、長門(現在の山口県)2か国のみの36万9千石に減封されてしまいました。 |
 |
 |
周防、長門に入った輝元は、関ヶ原の敗戦の責任をとって家督を嫡男の秀就に譲りました。秀就は幼かったため実権は輝元が握ったままでした。居城を築くため徳川幕府に山口、萩、防府の3ヶ所を候補として申請しました。 |
| 外様大名の毛利氏の勢力を削ぐため、幕府からは山陰の過疎地であった萩に許可を出したようです。以後約250年間、防長両国の政治の中心になり、明治維新には歴史的な重要拠点にもなったのでした。 |
 |
 |
萩城は日本海に張り出した指月山の詰の丸と、その山麓に梯郭式に本丸・二の丸・三の丸を配し三重の堀を巡らした平山城です。 |
| 外堀の内に三の丸、中堀の内が二の丸、内堀の内に本丸が設けられていたわけです。本丸には、天守閣、本丸御殿、櫓が、二の丸には櫓12棟が立ち並んでいました。 |
 |
 |
明治7年(1874)前年に発布された廃城令により天守や櫓などの建物が破却されてしまいました。本丸には高さ14、5mの五層の天守閣がありましたが、今はその台座のみが残っているだけです。 |
| 志都岐山神社前の庭池に架かる石橋は万歳橋と呼ばれ、藩校明倫館の聖廟前のはん水中央に架けられていた橋でした。江戸時代の藩校の貴重な遺構として、萩市の文化財に指定されています。 |
 |
 |
現在は指月公園として整備され、旧城の入り口には旧厚狭毛利家萩屋敷長屋(国の重要文化財)が往時の姿を偲ばせてくれます。 |
志都岐山神社
しずきやまじんじゃ
山口県萩市堀内

 |
志都岐山神社は萩城のあった指月公園の中央に位置しています。境内には維新にかかわる碑が数多く建てられています。 |
| 明治12年(1879)、萩の有志が山口市の豊栄神社(祭神は毛利元就)、野田神社(祭神は毛利敬親)の分社として、建立したものです。 |
 |
 |
その後、指月(しづき)神社といわれてきましたが、明治15年、現在の志都岐山(しづきやま)神社となったそうです。 |
| 毛利輝元を主祭、元就と敬親を配祀とし、隆元、輝元、元徳(もとのり)を加えて5柱として、初代から12代まで萩藩歴代藩主を祀っています。社務所は永代家老福原家の書院を移築したものです。 |
 |
 |
志都岐山神社前の庭池に架かる石橋は万歳橋と呼ばれ、藩校明倫館の聖廟前のはん水中央に架けられていた橋でした。江戸時代の藩校の貴重な遺構として、萩市の文化財に指定されています。
|
旧萩藩御船倉
きゅうはぎはんおふなぐら
山口県萩市東浜崎町

 |
御船倉は藩主の御座船(ござぶね)を繋ぎ留めておいた場所です。慶長13年(1608)萩城築城後、まもなく造られたとみられます。 |
| 間口8.8m、高さ8.8m、奥行き27mの大きな建物です。両側と奥を玄武岩で覆わせ、立派な屋根を葺き、前面はお城のような頑丈そうな木製扉です。 |
 |
 |
もとは大船倉を中央にして小船倉が左右にあったそうです。明治初期に壊されてしまい、現在は中央の大船倉だけが残っています。 |
| この浜崎には、 御船倉という役所が置かれていたそうです。御船倉は萩藩主の乗る 船を格納するだけではなく、 浜崎宰判(さいはん) という行政区域を治める代官所でもあったのです。 |
 |
旧周布家長屋門
きゅうすうけながやもん
山口県萩市堀内2区の2

 |
旧周布家長屋門は旧三の丸北の総門筋にあります。木造平屋建て本瓦葺きで江戸時代中期の代表的な武家屋敷長屋です。 |
| 周布家は萩藩の大組士筆頭の地位にありました。石見国周布郷の地頭職として周布村(島根県浜田市周布村)に居住していたことから周布を名乗ったそうです。 |
 |

 |
梁間4m、桁行25mという長い建物です。中央から東よりに通用門を設け、腰部を下見板張りとしています。 |
明倫館
めいりんかん
山口県萩市江向3区の1
TEL 0838-25-3139

 |
明倫館は享保4年(1719)に5代藩主毛利吉元(よしもと)によって萩城三の丸に創建された藩校です。 |
| 明倫館の名称は吉元の侍講、山県南周が命名しています。孟子の中の「皆人倫を明らかにする所以なり」からとったそうです。 |
 |
 |
嘉永2年(1849)に13代藩主毛利敬親(たかちか)によって現在の場所に移したそうです。敷地は約5万m2もあり、藩校としては水戸の弘道館、鹿児島の造士館と並ぶ大規模なものでした。 |
| 聖廟を中心に、初等から高等までの学問施設、医学所、武芸修練場など、大小47棟があり、設備、教育内容ともに全国有数で、多くの人材を輩出しました。 |
 |
 |
敷地内には現在の明倫小学校があります。観徳門や坂本龍馬が試合をしたという逸話のある剣術場と槍術場を移転して拡張した有備館が残っています。 |
| 有備館の奥には玄武岩の石垣で築いた水練池があり、水泳や水中騎馬の練習が行なわれたそうです。わが国に残存する唯一の遺構です。 |
 |
 |
明倫館は、水戸藩の弘道館、岡山藩の閑谷黌と並び、日本三大学府の一つと称されたそうです。 |
山口県立萩美術館・浦上記念館
やまぐちけんりつはぎびじゅつかん・うらがみきねんかん
山口県萩市平安古
Tel 0838-24-2400

 |
山口県立萩美術館・浦上記念館は萩出身の実業家、浦上敏朗氏のコレクションの寄贈を機に開館した美術館です。 |
| 萩の町並みを連想させる横長の平面や土塀を暗示する石の造形で、古い面影のある近代的な建物に仕上げています。 |
 |
 |
歌川広重の「東海道五十三次」をはじめ、安藤広重、葛飾北斎、歌川国芳、喜多川歌麿らの浮世絵約5000点を収蔵しています。また中国や朝鮮の陶磁器や青銅器類など500点も収蔵展示しています。 |
萩博物館
はぎはくぶつかん
山口県萩市大字堀内355
Tel 0838-25-6447

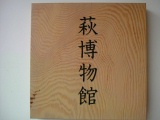 |
萩博物館は平成16年(2004)に萩開府四百年を記念して開館しました。武家屋敷風の大きな建物です。 |
| 旧萩城内にあたる堀内地区重要伝統建造物群保存地区内の大野毛利家上屋敷跡に建てられています。 |
 |
 |
4つの展示室を持っていて、城下町萩の自然や吉田松陰や高杉晋作らが活躍した幕末の資料など500点近くが収蔵、展示されています。 |
菊屋家住宅
きくやけじゅうたく
山口県萩市呉服町1−1
Tel 0838-25-8282

 |
菊屋家住宅は呉服町にあります。正面は 藩主の通行する御威道(おなりみち)側にあります。西側には菊屋横丁とよばれるなまこ壁の小路が続いています。 |
| 屋敷地には数多くの蔵や家屋が建てられていますが、主屋、本蔵、金蔵、米蔵、釜場の5棟は国の重要文化財に指定されています。 |
 |
 |
菊屋家の先祖は、毛利氏に従い広島、山口、萩に移ってきたそうです。萩藩の御用商人となり、萩の町割りも命じられたそうです。 |
| 代々大年寄格に任命され藩の御用達を勤めた豪商でした。屋敷は幕府巡検使の宿として本陣に当てられたほどでした。 |
 |
 |
主屋は17世紀中頃建てられたようです。桁行13m、梁間14.9mの切妻造りの建物で屋根は瓦葺きです。前寄り一間半を店にして、奥は土間寄りに役向きの部屋が3部屋設けられています。日本で最も古い大型の町家の一つです。 |
高杉晋作旧宅
たかすぎしんさくきゅうたく
山口県萩市呉服町

 |
高杉晋作旧宅は菊屋家の西の菊屋横丁にあります。「高杉春樹(晋作の父)舊宅地」と「高杉晋作誕生地」の2つの石碑が建っています。晋作は安政4年(1857)久坂玄瑞に勧められ松下村塾に通いました。 |
| 文久2年(1862)上海に渡り、中国の植民地化を目のあたりにして帰国しました。その後、品川英国公使館焼き討ち事件を起こし、文久3年(1863)下関で奇兵隊を組織して倒幕運動の中心的存在となりました。慶応元年(1865)下関で挙兵、幕府恭順派をうち破って藩内の主導権を握りましたが、(慶応3年(1867)志半ばで病に倒れてしまいました。29歳の若さでした。 |
 |
青木周弼旧宅
あおきしゅうすけきゅうたく
山口県萩市南古萩町2
Tel 0838-25-3139

 |
青木周弼旧宅は安政6年(1859)新築され、母屋は、来客用と家人用とに分けられています。周弼は、漢方医学を学んだ後に江戸でオランダ医学を修得しました。13代藩主の毛利敬親の侍医でもありました。 |
| 青木研蔵は周弼の実弟で、のちに養子となり家督を継ぎました。明治2年(1869)明治天皇の大典医になっています。周蔵は研蔵の養子でドイツ留学を機に外交官になり、山県有朋、松方正義内閣では外務大臣を務めました。 |
 |
円政寺
えんせいじ
山口県萩市南古萩町6
Tel 0838-22-3031

 |
円政寺は真言宗御堂派のお寺です。大内氏の祈願寺として山口にありましたが、毛利氏とともに萩に移った古刹です。 |
| 門前には「高杉伊藤両公幼年勉学之所」と刻んだ石碑が建っています。石灯篭は県下では最大のものです。 |
 |
 |
伊藤博文の母親と円政寺の住職が従兄妹の関係だったので1年半、博文はこの寺に預けられたそうです。当時使用したレンガのすずりやしょいこも展示されています。高杉晋作が肝だめしをしたという大きな天狗の面や、遊んだ木場(神馬)なども残っています。 |
木戸孝允旧宅
きどたかよしきゅうたく
山口県萩市呉服町2−37
Tel 0838-25-3139

 |
木戸孝允(桂小五郎)の生家は菊屋家住宅の1筋ほど東の江戸屋横丁にあります。孝允が誕生した部屋や浴室、庭などが残っています。 |
| 父親の和田昌景は萩藩医でした。そのため患者用と来客用の2つの玄関があり、当時としては珍しい木造2階建ての家でした。部屋も12あったそうです。孝允は天保4年(1833)に誕生し、20年ここで過ごしたようです。 |
 |
 |
孝允は桂九郎兵衛孝古(たかひさ)の養子となり、桂小五郎と称しました。明倫館や松下村塾に学び、西郷隆盛、大久保利通とともに維新の三傑となりました。 |
野山獄跡・岩倉獄跡
のやまごくあと・いわくらごくあと
山口県萩市古今萩町2

 |
安政元年(1854)海外密航に失敗した吉田松陰は野山獄に入れられ、一緒に行動した弟子の金子重輔は隣の岩倉獄に入れられました。 |
野山獄は上牢として上級武士を、岩倉獄は下牢として庶民が収容されていたそうです。
この場所には萩藩藩士野山家と岩倉家の屋敷がありました。道をはさんで建つ両家は、ともに萩大組で禄高は200石取りでした。 |
 |
 |
正保2年(1645)、酒に酔った岩倉孫兵衛が、野山六右衛門の家族を切ったため、両家とも取りつぶになりました。屋敷は藩に没収され、牢獄になったのです。 |
| 野山獄跡には十一烈士の碑、岩倉獄には重輔絶命の詩碑と松陰が重輔に与えた詩碑が建てられています。 |
 |
常念寺
じょうねんじ
山口県萩市下五間町17番地
Tel 0838-22-0006

 |
長栄山常念寺は浄土宗のお寺で、天文元年(1532)吉見家の家臣であった阿部家貞を開基として創建されています。 |
| 毛利輝元が、関ケ原の役後、萩築城の際に宿舎にしたそうです。その縁で表門を寛永10年(1633)に寄進されました。この門は輝元が豊臣秀吉から拝領したもので、京都の聚楽第の裏門だったそうです。国の重要文化財に指定されています。 |
 |
 |
この表門は本瓦葺きの屋根をもつ四脚門で、蟇股に豪放な桃山時代の特色の特徴が見られます。またこの寺には吉田松陰の屍体処理をした藩医飯田正伯などの墓があります。 |
熊谷家住宅
くまやけじゅうたく
山口県萩市大字今魚店47
Tel 0838-22-7547

 |
熊谷家住宅は明和5年(1768)に新築されたものと伝えられ、広大な屋敷に 主屋のほか離れ座敷、土蔵など10数棟が建ち並んでいます。 |
| 萩藩7代藩主毛利重就は藩の財政立て直しのため宝暦4年(1754)城下の商人の中 から熊谷五右衛門芳充を抜擢して所帯方御用達としました。 |
 |
 |
芳充はよく その期待にこたえて活躍し、大阪御用達であった鴻池や加島屋と同格の上方町人格に置かれるようほどになりました。後には市中大年寄にも任ぜられたそうです。 |
| 4代目の五右衛門義比は文化に造詣が深く、学者や文人墨客に経済的援助を惜しまなかったそうです。シーボルトとも親交があり、シーボルト愛用のピアノがこの蔵の中にあります。 |
 |
萩カトリック教会
はぎかとりっくきょうかい
山口県萩市土原3区564

 |
明治24年(1891)ビリヨン神父によって殉教した浦上キリシタンの墓と祈念碑が建てられました。ビリオン神父は明治22年(1889)に「パリ外国宣教会」から山口に派遣されていたのです。 |
| 明治28年(1895)、萩に赴任されたビリオン神父は、市内平安古の民家を教会して萩カトリック教会初代司祭になりました。 |
 |
 |
1965年、ヴイエラ神父が今の聖堂を建て、1994年には三浦神父がキリシタン墓地と祈念碑を改修し、「萩キリシタン殉教者記念公園」と名付けたのでした。 |
萩キリシタン殉教者記念公園
はぎきりしたんじゅんきょうしゃきねんこうえん
山口県萩市堀内1区の3

 |
明治元年(1868)に続いて明治3年(1871)、明治政府はキリスト教弾圧政策をとりました。浦上崩れとよばれ、長崎浦上村の全信徒3800人を全国各地に流刑しました。このうち300人近くが萩に流されたのです。 |
| 信仰篤い彼らを改宗させるために苛酷な拷問などが3年間も課せられたそうです。40人がそのために亡くなり20人が岩国屋敷だったこの場所に埋葬されていました。 |
 |
 |
明治24年(1891)萩カトリック教会初代司祭ビリヨン神父によって殉教した浦上キリシタンの墓と祈念碑が建てられたのです。またここにはキリシタン信者であったために藩によって処刑された、熊谷元直と天野元信の殉教碑も建てられています。 |
松下村塾
しょうかそんじゅく
山口県萩市船津の1

 |
松下村塾というのは松蔭が子供の頃に叔父の玉木文之進が開いていた塾です。文之進が藩から抜擢されたので松蔭の外叔の久保五郎左衛門があとを継ぎました。安政4年(1857)松蔭がそのあとを継いだのでした。 |
| この時、松蔭は幽囚の身であったのです。嘉永7年(1854)1月、ペリーの2度目の来航の際、金子重之助とともに密航計画を企て野山獄に幽囚されたあとでした。 |
 |
 |
ここで高杉晋作を初め久坂玄瑞、伊藤博文、山県有朋、吉田稔麿、前原一誠など、維新の指導者となる人材を教え育てました。門弟がふえたことから8畳の建物から10畳半の2間に増築しています。 |
| 安政5年(1858)年7月には藩から家学教育の許可もでましたが、幕府が勅許なく日米修好通商条約を結んだことで、老中の間部詮勝の暗殺を企て再び投獄されました。安政6年(1859)5月江戸に送られ、安政の大獄により処刑されてしまいました。29歳という若さでした |
 |
 |
この松下村塾は、杉家の物置小屋を改築したもので、質素な小さな建物です。藩が作った学校である明倫館へ入学できないような下級武士の子弟が多く学んだことも有名な話です。 |
松陰幽囚ノ旧宅
しょういんゆうしゅうのきゅうたく
山口県萩市大字椿東

 |
安政2年(1855)吉田松陰は保釈されて父親の預かりとなり一年半、この杉家の4畳半の幽囚室で講義を始めたそうです。その後松下村塾で一年間教え高杉晋作を初め久坂玄瑞、伊藤博文、山県有朋などを育てました。 |
| 吉田松陰は文政13年(1830)長州藩の下級武士の杉百合之助の二男として萩の松本村に生まれました。松陰には、他家に養子に行き家督を継いでいた長州藩の兵学師範(山鹿流兵学)であった吉田大助と松下村塾を興した玉木文之進という二人の叔父がいました。大助に跡継ぎがなかったため吉田家へ養子に入りました。大助が急死したため6歳にして吉田家の家督を継ぎ、藩校明倫館の兵学師範になる宿命を背負ったのです。 |
 |
 |
山鹿流免許皆伝であった玉木文之進の厳しい教育で11歳の時に、藩主毛利敬親の前で山鹿流「武教全書」を講義し天童と言われたのでした。 |
| 嘉永7年(1854)1月、ペリーの2度目の来航の際、金子重之助とともに密航計画を企て野山獄に幽囚、その後この幽囚室と松下村塾で講義を続けました。老中の間部詮勝の暗殺を企てたことで捕らえられ、江戸に送られ帰らぬ人となりました。 |
 |
松陰神社
しょういんじんじゃ
山口県萩市椿東松本
Tel 0838-22-4643

 |
松陰神社は、維新の原動力となった幕末の思想家で教育者でもあった吉田松陰を祭神とする神社です。現在の朱塗りの本殿は昭和30年(1955)に建てられたものです。 |
| 明治23年(1890)松陰の実家である杉家の邸内に松陰の実兄の杉民治が土蔵造りの小祠を建て、松陰の遺言により愛用していた赤間硯と松陰の書簡とを神体として祀りました。 |
 |
 |
明治40年(1907)松下村塾出身の伊藤博文と野村靖が中心となって神社創建を請願し、萩城内にあった鎮守の宮崎八幡の拝殿を移築して土蔵造りの本殿に増築させ、県社に列格しました。 |
創建当時の土蔵造りの旧社殿は「松門神社」として、松陰の門人であった人々の霊を祀っています。
松陰神社は萩市で学問の神として最も尊敬を集める神社であり、正月には多くの初詣客が訪れます。 |
 |
秋吉台
あきよしだい
山口県美祢郡秋芳町秋吉

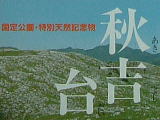 |
面積、およそ1万3千ヘクタールの日本最大の石灰岩台地が秋吉台です。標高200mから400mほどの起伏に富んだ草原状の台地には、白く露出する石灰岩柱が点在します。秋吉台には、このような大きな窪みが無数にあります。 |
| 約3億5千万年前から2億2千万年前に海底に堆積したフズリナ、サンゴ、石灰藻などの生物の遺骸などが地殻変動によって陸地になり石灰岩になったのです。
|
 |
 |
石灰岩は炭酸カルシウムという成分からできています。石灰岩台地に降る雨は空気中の二酸化炭素を含み込んで弱酸性の水となります。この水が、炭酸カルシウムでできている石灰岩に触れると化学反応をおこし、石灰岩を少しずつ溶かすのです。
|
| こうしてできた地形がカルスト地形とよばれ、ドリーネ、ウバーレ、ポリエなどの窪地を造っていくのです。そうして鍾乳洞が出来上がるのです。 |
 |
秋芳洞
あきよしどう
山口県美祢市秋芳町秋吉広谷
Tel 0837-62-0304

 |
石灰岩の台地、秋吉台の地下100mに総延長10kmの鍾乳洞があります。これがわが国最大級の鍾乳洞の秋芳洞で、国の特別天然記念物に指定されています。 |
| 約3億5千万年前から2億2千万年前に海底に堆積したフズリナ、サンゴ、石灰藻などの生物の遺骸などが地殻変動によって陸地になり石灰岩になりました。 |
 |
 |
石灰岩は炭酸カルシウムという成分からできています。石灰岩台地に降る雨は空気中の二酸化炭素を含み込んで弱酸性の水となります。この水が、炭酸カルシウムでできている石灰岩に触れると化学反応をおこし、石灰岩を少しずつ溶かすのです。 |
| こうしてできた地形がカルスト地形とよばれ、ドリーネ、ウバーレ、ポリエなどの窪地を造っていくのです。そうして鍾乳洞が出来上がるのです。 |
 |

 |
洞内にはコウモリ、アキヨシミズムシなどの固有種や珍しい生物が見られます。平成17年(2005)には、秋吉台地下水系がラムサール条約にも登録されました。 |
岩国城
いわくにじょう
山口県岩国市横山

 |
関ケ原の合戦後、毛利氏が防長二州に削封されたのに伴い、吉川広家は出雲国富田城から岩国に移り、慶長13年(1608)天守閣が建てられました。しかし元和元年(1608)一国一城令が出てわずか7年で破却されました。 |
| 現在の天守閣は昭和37年に再建されたものです。吉川広家は毛利元就の二男吉川元春の第三子です。吉川氏が初めて諸侯と列したのは明治3年(1803)岩国藩ができた時でした。 |
 |
吉香公園
きっこうこうえん
山口県岩国市横山2丁目

 |
吉香公園 は旧岩国藩主吉川家の居館跡にできました。明治13年(1880)から昭和43年(1968)まで旧制岩国中学校・山口県立岩国高等学校が建っていました。高校を別のところに移転させ、広い公園が誕生したのです。 |
| 吉香神社そばのエンジュなど山口県の天然記念物に指定されている樹木の中に、香川家長屋門、岩国徴古館、目加田家住宅、錦雲閣、吉香神社、岩国美術館、吉川史料館など藩政をしのばせる建物が点在しています。 |
 |

岩国徴古館
いわくにちょうこかん
 |
昭和20年(1945)に完成した石造り風の重厚な建物が岩国徴古館です。戦時中に建設され、レンガ造りですが、竹とコンクリートを用いた竹筋コンクリート造りです。平成10年(1998)に岩国市の登録有形文化財に指定されました。 |
| 館内では吉川家ゆかりの文書、歴史資料、美術工芸品などが展示されています。錦帯橋のコーナーには昭和25年(1950)にキジア台風で流失した錦帯橋の欄干や、模型なども展示されています。 |
 |
錦雲閣
きんうんかく
 |
錦雲閣は明治18年(1885) に旧岩国藩主吉川家の居館跡が公園として開放された時に、旧藩時代の矢倉に似せて建てられた絵馬堂です。 |
| 緑豊かな吉香公園の中にあり、堀に面して建つ姿は趣があります。桁行6間梁行4間、身舎5間×3間の入母屋造です。桟瓦葺で楼閣風建築です。 |
 |

 |
平成12年(2000)に岩国市の登録有形文化財に指定されました。国の登録文化財でもあります 。 |
白蛇横山観覧所
しろへびよこやまかんらんじょ
| 岩国の天然記念物であるシロヘビを公開しています。このヘビは江戸時代にアオダイショウの変種が金運を授ける神蛇として保護され、増えたものといわれています。 |
 |
旧目加田家住宅
きゅうめかたけじゅうたく
 |
吉香公園の中にある目加田家住宅は江戸時代中期に建てられた中級武士の屋敷です。桁行16.4m、梁間11.6mの入母屋造りです。南側に玄関があり、北面に風呂場が付いています。 |
| 現在でも当時の状態をよく残しています。簡素ながら端正な構造で、昭和49年(1974) に国の重要文化財に指定されています。 |
 |
岩国美術館
いわくにびじゅつかん
 |
戦国時代から幕末にかけて大名たちが所用していた武具の展示館です。 |
| 奈良時代から江戸時代までの甲冑、刀剣などの、国重要文化財、県や市の指定文化財など18件を含む約4500点が展示されています。 |
 |
吉香神社
きっこうじんじゃ
山口県岩国市横山2ー8ー10
Tel 0827-41-0600

 |
慶長5年(1600)毛利氏が防長二州に削封されたのに伴い、吉川広家は出雲国富田城から岩国に移りました。そしてここに居館を構え、正徳年間に本社をこの地へ奉遷し、社殿を造営しました。 |
| 吉川家の先祖を祭る神社は、もともと治功大明神(吉川興経)、高秀神社(吉川経義)、鎮照神社(吉川広家)の3社でした。明治7年(1874)本社を後世に残すために認可をうけ、8神を合祀して吉香神社と称しました。 |
 |
 |
吉香神社は岩国藩主吉川氏歴代の神霊を祀る神社です。現社殿は、享保13年(1728)横山の白山神社境内に造営され、明治18年(1855)に旧城跡の現在地に移築されたものです。 |
| 鳥居、神門、拝殿及び幣殿、本殿が南から北に一直線に並んでいます。神門は小型の四脚門で冠木中央に吉川家家紋があります。拝殿は、入母屋造で背面に幣殿が張り出し、本殿は、三間社流造で正面に軒唐破風、千鳥破風が付されています。 |
 |
 |
本殿、拝殿、神門が同一時期の建築でそろっているものは大変貴重です。昭和63年(1988)県の有形文化財に指定され、平成16年(2004)国の重要文化財に指定されました。 |
錦雲閣
きんうんかく
山口県岩国市横山2 吉香公園内

 |
錦雲閣は明治18年(1885) に旧岩国藩主吉川家の居館跡が公園として開放された時に、旧藩時代の矢倉に似せて建てられた絵馬堂です。 |
| 緑豊かな吉香公園の中にあり、堀に面して建つ姿は趣があります。桁行6間梁行4間、身舎5間×3間の入母屋造です。桟瓦葺で楼閣風建築です。 |
 |
 |
平成12年(2000)に岩国市の登録有形文化財に指定されました。国の登録文化財でもあります。 |
旧目加田家住宅
きゅうめかたけじゅうたく
山口県岩国市横山2 吉香公園内

 |
吉香公園の中にある目加田家住宅は江戸時代中期に建てられた中級武士の屋敷です。桁行16.4m、梁間11.6mの入母屋造りです。南側に玄関があり、北面に風呂場が付いています。 |
| 現在でも当時の状態をよく残しています。簡素ながら端正な構造で、昭和49年(1974) に国の重要文化財に指定されています。 |
 |
 |
目加田家住宅は平屋建てのように見えますが二階があります。表側は大屋根として藩主が前を通った時、見下ろすことがないように配慮した造りといわれています。 |
香川家長屋門
かがわけながやもん
山口県岩国市横山2 吉香公園内

 |
香川家長屋門は岩国藩家老の香川氏の表門で、元禄6年(1693) に香川正恒が建立したと伝えられています。岩国市の建造物としては最も古いものの一つで、当時の武家屋敷の構えをよく残しています。 |
| 瓦に1個づつ家紋が刻してある長屋門の他に、通用門、平時門などがあり、身分、用件によって使いわけられていたそうです。昭和41年(1966) に山口県の有形文化財に指定されています。 |
 |
吉川史料館
きっかわしりょうかん
山口県岩国市横山2ー7ー3 吉香公園内
Tel 0827-41-1010
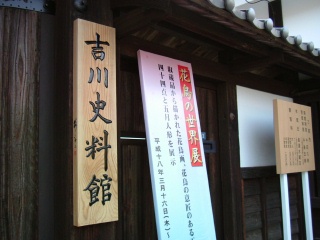
 |
約800年の歴史をもつ吉川家に代々伝わる武具、甲冑、刀剣、美術工芸品や歴史資料を収蔵し順次公開しています。吉川家文書、吾妻鏡、永禄6〜8年に吉川元春筆写した太平記など、約2500点の重要文化財をはじめ、国宝の太刀「狐ヶ崎」なども所蔵しています。 |
| 吉川氏は周防国岩国藩の藩主です。吉川家は、藤原氏南家の支流で、駿河国入江庄に住んで、入江氏を称した維清3代の孫、入江景義の嫡男経義が、寿永・文治の頃(1183-86)入江庄吉川(静岡県清水市)に居館を構えて、吉川と称したのが始まりといわれています。 |
 |
 |
駿河から安芸国に移つり、南北朝の内乱の時は一族が南北に分裂しましたが国人領主として発展し、室町時代の末に毛利氏に帰属しました。13代元経の妻は、毛利元就の妹であり、元就の妻は、元経の妹でした。これより、吉川と毛利とは深いつながりができていました。 |
| 元就の次男元春が、14代興経の養子となり、吉川家を継いでからは、小早川隆景(元春の弟)とともに、宗家を助け、世に毛利の両川と称されました。毛利家の家老格に扱われていたため正式に諸侯に列せられたのは明治になってからでした。 |
 |
錦帯橋
きんたいきょう
山口県岩国市岩国

 |
錦帯橋は、山口県岩国市の錦川に架橋された木造のアーチ橋です。延宝元年(1673)岩国藩三代藩主吉川広嘉により建設されました。 |
| 日本3名橋や日本3大奇橋に数えられており、名勝に指定されています。5連のアーチからなるこの橋は、全長193.3m、幅員5mで、継手や仕口といった組木の技術によって造られています。 |
 |
 |
吉川広嘉は洪水の起きやすい錦川に流れない橋を架ける算段をしました。橋脚のない甲斐の跳ね橋(刎橋)「猿橋」に着目しますが、約30mの猿橋とは条件が違いすぎ、応用することをあきらめました。 |
| 広嘉は明の渡来僧である独立(どくりゅう)から中国の杭州、西湖にある「錦帯橋」の知識を得ます。島づたいに石橋が架かっているのを絵で見て、連続したアーチ橋を架けたらどうかと考えました。 |
 |
 |
洪水にも耐えられるようにアーチ間の橋台を石垣で築くことにして、児玉九郎右衛門に架橋を命じました。 |
| そして延宝元年(1673)、岩国藩の悲願であった錦帯橋がついに完成しました。しかし翌年洪水により一部が流されてしまいました。 |
 |
 |
その年のうちに、敷石を強化し再建したところ強固な橋になり、それ以後276年の間、補修や架け替えは行なわれましたが、流されることはなかったのです。 |
| しかし昭和25年(1950)9月、キジア台風による大増水により、惜しくも流失してしまいました。昭和28年 (1953)市民の熱意で再建されました。 |
 |
 |
平成13年(2001) 秋より「平成の架け替え」が行なわれ、平成16年(2004) 3月、5つの反り橋は生まれ変わりました。岩国の匠の手により昔ながらの木組みの工法で施工されたのです。 |
| 槍倒し松 |
紅葉谷公園
もみじだにこうえん
山口県岩国市横山

 |
「紅葉谷公園」一帯は、昔は寺谷といわれ、寺院が集まっていた場所だったそうです。公園内には約1000本のモミジが植えられ、秋は紅葉の名所として有名で「西の鎌倉」とも呼ばれているそうです。 |
| 紅葉谷公園の一角に 「六角亭」と呼ばれる建物があります。岩国出身で朝鮮総督を務めた長谷川好道元帥が朝鮮から贈られたそうです。大正7年(1918)にここに移築したそうです。また僧独立(どくりゅう)の碑などもあります。 |
 |
吉川家墓所
きっかわけぼしょ
山口県岩国市横山
 |
紅葉谷公園の入口に旧岩国藩主吉川家代々の墓が立ち並ぶ「吉川家墓所」があります。初代吉川広家から12代経幹までの当主や一族の墓が並んでいます。 |
| 8代藩主吉川経忠(つねただ)の墓です。悪化した岩国藩の財政を、文武教育の奨励し、敬神崇祖の範を示すことによっての土風刷新を図りましたが38歳という若さで亡くなりました。 |
 |
 |
11代藩主吉川経章(つねあきら)の墓です。兄で第10代藩主の吉川経礼が死去したため、兄の養子として家督を相続しました。 |
| 7代藩主吉川経倫(つねとも)の墓です。徳山藩5代藩主毛利広豊の九男として、江戸で生まれました。第6代岩国藩主吉川経永の男子はいずれも早世したため、吉川氏の一族以外から継嗣として迎えられました。 |
 |
 |
2代藩主吉川広正、3代藩主吉川広嘉、9代藩主吉川経賢の墓です。広正の正室は毛利輝元の娘・竹姫(高玄院)でした。竹姫は一度も岩国を訪れることはなかったそうです。 |
普賢寺
ふげんじ
山口県光市室積 8ー6ー1
Tel 0833-79-1223

 |
峨嵋(がび)山普賢寺は臨済宗のお寺です。寛弘3年(1006)に性空上人(しょうくうしょうにん)によって創建されたそうです。 |
| 普賢菩薩をみたいと念願していた上人が仏の導きで室積に来たそうです。海から引き上げられた網の中に木像があり、それが夢の中の普賢菩薩だったことから本尊として祀ったそうです。 |
 |
 |
室積(御手洗)湾に向かって建っている立派な楼門(仁王門)には左右に仁王像があり、楼上には十六羅漢像が安置されています。1798年に建立されたといわれています。 |
| 「海の守り菩薩」として広く信仰を集めていて、普賢菩薩像のご開帳は50年に1度だそうです。 |
 |
 |
境内には平康頼が鹿ケ谷の陰謀(1177)に連座して奇界ヶ島に流される途中、普賢寺に寄り出家したたいう石碑が建てられています。 |
| 仁王門の左手には、普賢寺の本堂があり、雪舟作といわれる枯れ山水的な庭園があります。ソテツが配された石組みの庭です。 |
 |
 |
山口県下でも古い枯山水庭園で、山口の常栄寺庭園、宇部の宗隣寺庭園と並んで紹介されています。 |
伊藤公資料館
いとうこうしりょうかん
山口県光市束荷2250−1
Tel 0820-48-1623

 |
伊藤公資料館は初代内閣総理大臣の伊藤博文の生誕地に建てられた資料館です。館内には伊藤公が使用した調度品や、旧千円札の第1号券なども展示されています。 |
| ここでは遺品や映像などで伊藤博文の生涯の軌跡を知ることができます。一帯は伊藤公記念公園になっています。 |
 |
 |
資料館のほかにも伊藤博文の生家や旧伊藤博文邸(伊藤公記念館)、また銅像なども建てられています。 |
| 伊藤博文は熊毛郡束荷村(現・光市、旧・大和町)に林十蔵、琴子の長男として生まれたました。萩に引っ越した後、父が伊藤家の養子となったため伊藤姓になりました。 |
 |
 |
吉田松陰の松下村塾に学び、桂小五郎、高杉晋作らとともに尊王攘夷運動に参加しました。文久3年(1863)イギリスに留学した後は開国、倒幕に論を転じました。 |
| 明治維新後に明治政府の中心人物として活躍し、大日本帝国憲法の制定や国会の開設に力を注ぎ、日本近代化の礎を築きました。 |
 |
 |
伊藤公資料館は、生家と旧伊藤博文邸の間に建てられています。鉄骨造り平屋建、534.36平方mで、レンガ造りの明治風建築となっています。 |
| 伊藤公資料館 |
| 旧伊藤博文邸は、伊藤自らが基本設計したルネッサンス風の建物です。明治43年(1910)に完成しましたが、その前の年にハルビンで暗殺されてしまいました。建物は、後に伊藤家から山口県へ寄贈され、さらに当時の大和村に無償で払い下げられました。 現在は、県指定文化財として保存されています。 |
 |
| 旧伊藤博文邸 |
花岡八幡宮
はなおかはちまんぐう
山口県下松市花岡400
Tel 0833-44-8570

 |
花岡八幡宮は和同2年(709)に、豊前国(大分県)宇佐八幡宮の分霊を歓請して創建された由緒ある神社です。 |
| 慶長4年(1599)には地蔵院・楊林坊・常福坊・千手院・閼伽井坊・香禅寺・惣持坊・長福寺・関善坊の9坊を擁していたことが確認されているそうです。 |
 |
 |
江戸末期には地蔵院と閼伽井坊の2坊だけとなったそうです。地蔵院は明治2年に住僧の還俗により廃院となり、現在は閼伽井坊のみが現存しています。 |
| 花岡八幡の楼門から本殿の参道右に坊舎で唯一残った閼伽井坊の管理(所有)とされている多宝塔があります。 |
 |
 |
日本16塔の1つに数えられ国の重要文化財の閼伽井坊塔婆(多宝塔)です。高さ13.5mの二重の塔は優美な姿を見せてくれます。 |
| 伝来する室町時代末期から安土桃山時代までの花岡八幡宮文書は60通をかぞえ、豊臣秀次朱印状のほか大内義隆、陶隆房(晴賢)、毛利元就等の判物等を含んでいます。 |
 |
 |
拝殿には、従一位近衛忠熈卿の筆による「永受嘉福」の扁額や、江戸時代の風俗がよくわかる御神幸絵図などが奉納されています。 |
| 花岡八幡宮は桜の名所としても知られ、開運厄除や交通安全の神として信仰を集めています。 |
 |
閼伽井坊塔婆
あかいぼうとうば
山口県下松市花岡戎町

 |
花岡八幡宮の境内には国の重要文化財の閼伽井坊塔婆多宝塔があります。
日本十六塔の一つに数えられ国の重要文化財に指定されています。 |
| この多宝塔は元は花岡八幡宮の坊である地蔵院に属していましたが、地蔵院が廃寺になった為に今では唯一残っている閼伽井坊(あかいぼう)に属しています。建立は室町時代と思われますが、地蔵院の火災で古文書が消失し詳しい事が分らなくなっています。 |
 |
 |
閼伽とは仏教用語で仏様に供える水の事をさし、閼伽井はその水を汲む井戸の事で、閼伽井坊の中にあります。 |
太陽寺
たいようじ
山口県周南市大字八代171
Tel 0833-91-0204

 |
水上山太陽寺は釈迦如来を本尊とする曹洞宗のお寺です。貞和3年(1347)に建立された古刹です。毛利氏一門の宍戸氏の領地となり宍戸家代々の牌所となっています。 |
| 深川(現長門市)の大寧寺(たいねいじ)岩国の永興寺(ようこうじ)などとともに、防長の曹洞宗4古刹と称されています。 |
 |
 |
裏庭の心字池は「御恩返しの雷の水」と呼ばれ不思議な伝説が残っています。他にも池の水が枯れないなど7不思議が伝えられています。 |
防府天満宮
ほうふてんまんぐう
山口県防府市松崎町14番1号
Tel 0835-23-7700

 |
防府天満宮は京都の北野天満宮、福岡の太宰府天満宮と並んで、「三天神」といわれています。「松崎天満宮」「松崎神社」などともいわれましたが、昭和28年(1953)防府天満宮に戻されたそうです。 |
| 菅原道真を学問の神様として祭った天満宮で、道真が亡くなった翌年の延喜2年(904)に出来た歴史のある天満宮です。 |
 |
 |
菅原道真が藤原時平の讒言によって左遷させられ時、しばらくこの松崎に滞在したそうです。防府市は天満宮を中心に栄え、天満宮の行事での来訪者が多い所です。 |
| 建久6年(1195)、俊乗房重源(しゅんじょうぼうちょうげん)が東大寺再建の礼として朱塗りの本殿回廊楼門を建立しました。 |
 |
 |
現在の社殿は昭和38年(1963)に再建されたものだそうです。拝殿の脇に春風楼があります。萩藩10代藩主毛利斉煕(なりひろ)が五重塔を建てようとしましたが資金の調達ができず重層の楼閣に変更されたそうです。 |
毛利氏庭園
もうりしていえん
山口県防府市多々良1ー15ー1
Tel 0835-22-0001

 |
明治4年(1871)の廃藩置県で藩主たちは東京に集められましたが、後に元いた領地に戻って住んでもよいことになりました。 |
| そこで明治25年(1892)、井上馨が旧萩藩主邸を建設する責任者となり、本宅の構想が練られ、ここ多々良(たたら)山の南麓の地が選び工事を始めました。 |
 |
 |
日清・日露戦争のため工事が大幅に遅れ、大正5年(1916)にようやく完成したそうです。
毛利氏庭園は平成8年(1996)に国の名勝に指定されています。 |
| この庭園は、約8万4千平方mの広大な敷地に、約4千平方mの豪壮な邸宅がある回遊式庭園です。中雀門(ちゅうじゃくもん)から内庭に入ると、瓢箪池を中心とした広大な庭に圧倒されます。 |
 |
 |
庭園は本邸にいたるまでのクロマツの並木を配した路傍庭園で、邸内の平庭と林泉(りんせん)と呼ばれる木立や泉水がある庭から構成されています。平庭は各建造物に調和するように各所に配置されていて、客殿の書院の南側にある平庭が最も豪華です。 |
毛利博物館
もうりはくぶつかん
山口県防府市多々良1ー15ー1
Tel 0835-22-0001

 |
毛利博物館は、毛利氏庭園の中にある博物館です。公爵の地位にあった旧萩(長州)藩主毛利氏の本邸を博物館として公開しています。 |
| 大正5年(1916)に建てられたこの邸宅は総ヒノキ造りの壮大な建築です。明治25年(1892)、井上馨によって構想が練られ、ここ多々良(たたら)山の南麓の地が選ばれました。 |
 |
 |
日清・日露戦争のため工事が大幅に遅れ、大正5年(1916)にようやく完成したそうです。本邸は広さ約4,000m2におよぶ豪邸です。 |
| 御殿造りの様式を取り入れた近代建築で木曾のヒノキ、屋久島のスギ、台湾のケヤキなど当時の最良の用材が使われています。明治、大正の建築・造園の技術の粋がつくされています。 |
 |
 |
ここには毛利元就ゆかりの品をはじめ、雪舟筆「紙本墨画淡彩四季山水図(国宝)、「古今和歌集第八」(国宝)など国宝4件7点、「紙本著色毛利元就像」をはじめ「毛利家文書」など9件の重要文化財など2万点にも及ぶ資料や文化財が収蔵されています。 |
種田山頭火 生家
たねださんとうかせいか
山口県防府市八王子2丁目

 |
種田山頭火は山口県西佐波令村(現在の山口県防府市大道)の大地主の家に生まれました。昭和の芭蕉とも呼ばれ、自由律俳句の代表として、同じ荻原井泉水門下の尾崎放哉と並び称されています。 |
| 生活苦から自殺未遂をおこし報恩禅寺住職に助けられ寺男となりました。大正15年(1925)寺を出て雲水姿で西日本を中心に旅をして句作を行ないます。昭和7年(1932)郷里の山口の小郡町(現在の山口市小郡)に「其中庵」を結庵。昭和14年(1938)松山市に移住し「一草庵」を結庵。翌年、そこで客死したそうです。 |
 |
周防国分寺
山口県防府市国分寺町2-67
Tel 0835-22-0996

 |
周防国分寺は周防灘(すおうなだ)に面し、古代から水陸交通の要衝として栄えた防府にあります。聖武天皇の勅願により、国ごとに建てられた官寺のひとつです。 |
創建当初の境内に今も伽藍を残すきわめて珍しい例として知られています。
周防国分寺は少なくとも、天平勝宝8年(756)には存在していたことが記録されているそうです。 |
 |
 |
松や楠の巨木が茂る境内地は国の史跡に指定されています。仁王門、金堂は毛利氏の再建で金堂は国の重要文化財に指定されています。 |
| この金堂は7代藩主毛利重就(しげたか)により安永8年(1779)に再建されたものだそうです。金堂には、藤原時代初期の木造日光・月光菩薩立像をはじめ多くの仏像、宝物があります |
 |
 |
桁行7間(約22m)梁間(はりま)4間(約15m)、屋根を二重とした大きな建物です。平面構成・規模や須弥壇(しゅみだん)などに中世以前の様式をよく伝えています。 |
| 須弥壇の中央に安置されている本尊薬師如来坐像も国指定重要文化財です。 像高195.1cm、膝張り161.3cm、左手に薬壺(やっこ)を乗せています。 |
 |
 |
この薬師如来坐像の中から見つかった左手の仏手は、応永24年(1417)の火災で焼失した旧本尊のものと伝えられ、製作時期は平安時代にさかのぼります。 |
| この仏手は重さが5kg、長さが64cmあり、今の薬師如来坐像のより大きな手であって、当時の仏像は今のものよりひとまわり大きかったことを物語っています。 |
 |
瑠璃光寺
るりこうじ
山口県山口市香山町7ー1
Tel 083-922-2409

 |
保寧山瑠璃光寺は曹洞宗のお寺です。守護大名であった大内氏の家臣の陶(すえ)弘房の夫人は戦死した夫のために吉敷(よしき)郡仁保庄に安養寺を建立し、後に瑠璃光寺に改めました。 |
| それより先、現在瑠璃光寺がある場所に、大内氏25代の大内義弘は香積寺を建立していました。義弘は応永6年(1399)応永の乱を起こし足利義満に敗れて戦死してしまいます。 |
 |
 |
弟の26代大内盛見(もりはる)は兄の霊を弔うため五重塔の建設を始めました。盛見自身も九州の少弐氏・大友氏との戦いで永享3年(1431)に戦死してしまいます。五重塔はその後嘉吉2年(1442)頃、完成したそうです。 |
| この五重塔は30年もの歳月をかけて完成されたことになります。国宝に指定されていて、全国で10番目に古く、屋根は30年ごとに葺き替えられています。大正5年(1916)に塔を解体修理した時、組物の斗に嘉吉2年と書かれた墨書が発見されたため時代を解明できたそうです。 |
 |
 |
慶長9年(1604)、毛利輝元が萩へ移ったため、香積寺を萩に引寺しました。解体して萩城内の別業四本松邸の資材としたそうですが、五重塔は山口の人々の要望で香積寺の跡地に残されたのです。その跡地に仁保から瑠璃光寺を移築されたのです。 |
| 高さ31.2mで屋根は檜皮葺、2層にのみ回縁(まわりえん)がついています。法隆寺と醍醐寺とともに日本三名塔の一つに数えられ、室町中期における最も秀でた建造物と評されています。 |
 |
香山墓所(萩藩主毛利家墓所)
かやまぼち(はぎはんしゅもうりけぼしょ)
山口県山口市香山町7

 |
階段の下の石畳は「鶯張りの石畳」といわれています。音が石段や石垣に反響して「きゅっ」という音がでます。 |
| 国指定史跡に指定されている香山墓所は正式には萩藩主毛利家墓所です。広大な地に整然と配置され、萩市の天樹院、大照院、東光寺とともに長州藩主の墓所となっています。 |
 |
 |
香山墓所は、明治維新当時の当主であった13代毛利敬親(たかちか)夫妻、14代夫妻、15代夫妻など毛利本家歴代諸霊の墓の計7基と初代秀就の母周慶寺殿の墓があります。 |
洞春寺
とうしゅんじ
山口県山口市水の上町5ー27
Tel 083-922-1028

 |
正宗山(しょうしゅうざん)洞春寺は臨済宗建仁寺派のお寺です。明治元年(1868)萩城内から移した毛利元就の菩提寺です。応永11年(1404)大内盛見(もりはる)が祈願所として建立した国清寺が前身です。 |
| 毛利氏が防長に移ってからは、毛利隆元の菩提寺となりましたが、後に元就の菩提寺となり洞春寺と称しました。どっしりとした四脚門の山門は国清寺創建当時のもので、国の重要文化財に指定されています。 |
 |
 |
元の洞春寺は元亀3年(1572)、毛利輝元が祖父の元就の菩提寺として安芸吉田の城内に開基し、開山僧は嘯岳鼎虎(しょうがくていこ)禅師でした。慶長8年(1564)に毛利に従って山口に、次いで慶長11年(1567)に萩城内に移り、幕末に再び山口に移ったのでした。 |
| 現在の洞春寺本堂は、江戸時代に焼失して再建されたものです。洞春寺観音堂は上宇野令滝の観音寺にあったもので、国の重要文化財に指定されています。観音寺は大内義弘の子持盛の菩提寺で、後に勝音寺となり、毛利氏の時代になってからは大通院と称していました。大正4年(1915)に洞春寺に移築されたものです。 |
 |
 |
観音堂は桁行3間、梁間3間、1重もこし附入母屋造りの建物で、永享2年(1430)建立ということが厨子裏の板銘から判明したそうです。花頭窓や桟唐戸などが美しい唐様の建物です。 |
八坂神社(築山館跡)
やさかじんじゃ(つきやまやかたあと)
山口県山口市上竪小路100
Tel 083-922-0083

 |
八坂神社の境内地は築山館(つきやまやかた)といわれ築山神社などもあり、かって大内氏が政務をとっていた頃の勢力を偲ぶことのできる場所です。大内教弘が築山殿と称されていた時代に造られたと考えられています。 |
| 八坂神社は朱色の大鳥居がある神社です。応安2年(1369)、24代大内弘世が、京都の八坂神社を勧請しました。 |
 |
 |
現在の本殿は永正17年(1520)に30代大内義興(よしおき)が再建したもので、三間社流造りの見事なものです。室町時代の様式をよく伝えていて、国の重要文化財に指定されています。 |
| 本殿が再建された地は、鴻ノ峰の山口大神宮境内にありましたが、元冶元年(1864)、江戸時代末に毛利敬親によって現在の場所に移されました。 |
 |
 |
本殿には13個の変化に富んだ蛙股があります。この八坂神社の蛙股は形が優美で、他に類例の少ない珍しい図柄、花や果物、雲などが彫刻されています。 |
| 築山館は大内氏滅亡後朽廃しましたが、園池の跡は残っていたといわれています。しかし、この池も江戸時代中頃周囲の築地の土をもって埋めてしまい、現在のようになったといわれています。 |
 |
 |
毎年7月20日から行なわれる山口祇園祭では、室町時代から受け継がれてきた鷺舞(さぎまい)神事が奉納されるそうです。 |
今八幡宮
いまはちまんぐう
山口県山口市八幡馬場22
Tel 083-922-0083

 |
今八幡宮の創建年代は不明ですが、室町時代に記された「二十二社註式」によれば、初め宇治皇子一座を祀り今八幡宮と称しとあることから守護大名大内氏の山口入府以前からあったようです。 |
| 文亀3年(1503)、30代大内義興が、下宇野令の朝倉八幡宮を今八幡宮の地に移し、二社を合併して造建したのが現在の社殿であると伝えられています。 |
 |
 |
楼門、拝殿、本殿が一直線に配置されていて、楼門と拝殿を兼ねた作り方は山口地方独特の形式です。明との交易で得た莫大な財力を象徴する荘厳な建物で、国の重要文化財に指定されています。 |
| 大内氏滅亡後も、毛利氏により篤く保護され、神領が寄進されました。幕末には、社務所において堀真五郎、久坂玄瑞らが密談を重ね、八幡隊が結成され、屯所にもなったそうです。 |
 |
龍福寺
りゅうふくじ
山口県山口市下堅小路119
Tel 083-922-1009

 |
瑞雲山龍福寺は弘治3年(1667)、毛利隆元が大内義隆の菩提寺として建立したものです。一帯は大内氏の居館(大内館)跡で、国の史跡に指定されています。 |
| 本堂は弘治3年(1557)に建立されましたが、明治14年に焼失してしまいました。そこで、大永元年(1521)、大内義興が建立した興隆寺釈迦堂を移築して本堂にしたそうです。 |
 |
 |
文明11年(1479)に建立されたとみられるこの龍福寺本堂は国の重要文化財に指定されています。 |
| 大内氏館は、大内氏24代の弘世が南北朝期に築いたといわれています。その後8代、約200年に渡って大内氏の居館になり、大内文化の中心地でした。 |
 |
 |
龍福寺境内にある龍福寺史料館には、大内氏館跡から出土した品々、大内義隆画像などが展示されています。 |
旧山口藩庁門
きゅうやまぐちはんちょうもん
山口県山口市滝町1ー1(山口県庁)

 |
旧山口藩庁門は山口県庁の敷地内にある脇門付薬医門です。文久3年(1863)、毛利敬親(たかちか)は、今の県庁の位置に藩庁の移転を計画し、慶応3年(1867)に竣工しました。この門はその藩庁の正門でした。 |
| 一間一戸脇門付薬医門で、切妻造り、本瓦葺です。桁行10.28m、梁間2.86m、棟高6.84mで堂々とした城門らしい風格があります。 |
 |
旧県会議事堂
きゅうけんかいぎじどう
山口県山口市滝町1ー1
Tel 083-933-2268

 |
山口県の県会議事堂は旧県庁舎と一体となって保存されています。大正時代のレンガづくりの公共建築物としては数少ない建物です。 |
| 現在、旧議事堂は議会資料館として、旧県庁舎は県政資料館として、一般に公開されています。 |
 |
 |
レンガ組で銅滓(どうし)瓦葺きの堂々とした建物です。
後期ルネッサンス様式の西洋の建築様式と伝統的な和様式が融合しています。 |
| 大正建築の粋を集めた貴重な建築物として、2棟とも国の重要文化財に指定されています。 |
 |
 |
設計は後に国会議事堂を手がけた妻木頼黄部長以下、武田五一、大熊喜邦の二人が担当したそうです。 |
山口県政資料館
やまぐちけんせいしりょうかん
山口県山口市滝町1ー1
Tel 083-933-2268

 |
山口県政資料館は大正5年(1916)に建てられた、旧山口県庁舎と旧県会議事堂を公開した施設です。レンガ組で銅滓(どうし)瓦葺きの堂々とした建物です。 |
| 後期ルネッサンス様式の西洋の建築様式と伝統的な和様式が融合しています。大正建築の粋を集めた貴重な建築物として、2棟とも国の重要文化財に指定されています。 |
 |
 |
設計は後に国会議事堂を手がけた妻木頼黄部長以下、武田五一、大熊喜邦の二人が担当したそうです。 |
| 昭和59年(1984)現在の山口県庁舎が完成後は資料館として当時の知事室等の展示や県の概要に関する展示が行われています。 |
 |
山口県立美術館
やまぐちけんりつびじゅつかん
山口県山口市亀山町3ー1

 |
山口県庁のそばに昭和54年(1979)に開館した山口県立美術館があります。山口県出身の画家、香月泰男の作品が遺族により山口県に寄贈されたのをきっかけにして建てられたものだそうです。 |
| 香月画伯のシベリアシリーズはシベリアの抑留体験を描いた作品です。ここには長州藩とゆかりの深い雪舟や、狩野芳崖の作品も収蔵されています。 |
 |
山口県護国神社
やまぐちけんごこくじんじゃ
山口県山口市大字宮野下1932

 |
山口県護国神社は山口県関係の明治維新以降の国難に殉じた護国の英霊を祀っています。日清戦争以降、山口県出身の殉国の英霊を慰霊するため、明治36年(1903)防長靖献会が設立されました。以後、隣接する桜畠練兵場で盛大な招魂祭が行なわれてきたのが土台になっています。 |
| 昭和14年(1939)山口県にも護国神社を創建することとなり、昭和16年(1941)現在地に社殿が竣工されました。祭神の中には、吉田松陰、久坂玄瑞、来島又兵衛、大村益次郎、高杉晋作なども含まれています。 |
 |
 |
第二次大戦後は、山口県出身の殉職自衛官も合祀していますが、勤務中の交通事故で亡くなった中谷自衛官がキリスト教徒だったことから「自衛官護国神社合祀事件」が最高裁判所までいって争われています。 |
古熊神社
ふるくまじんじゃ
山口県山口市古熊1ー10ー3
Tel 083-922-0881

 |
古熊神社は応安6年(1373)に大内弘世が、京都の北野天神を勧請し、山口北野小路に祀ったのが始まりです。祭神は菅原道真で福部童子を配神としています。福部童子は道真の息子で11歳のときに、左遷先の父がいる太宰府へ向う途中、山口で病に倒れ亡くなり今市の甘露院に葬られました。 |
| 古熊神社が創建したあとは配神として祀られたのです。その後、古熊神社は数度の遷座を経て長者山の麓の御石の森に移りました。そして元和4年(1618)、毛利秀就が現在のこの地に社殿を移し、「今天神」と呼ばれました。 |
 |
 |
本殿および拝殿は室町時代に建立されたものを、ここに移築したもので、国の重要文化財に指定されています。境内は梅、桜の名所として知られ、8月25日には福部祭、11月22、23日には山口天神祭が執り行われています。 |
| 古熊神社の本殿は室町時代の天文16年(1547)の厨子銘があり、その頃に建てられています。三間社、入母屋造り、銅板葺き(もとは三間社流造り、屋根檜皮葺き)です。正面3間、側面2間、組物出3斗、中備蟇股、2軒繁垂木、妻叉首組前1間通り外陣正面吹放し、内外陣境にも組物を飾っています。 |
 |
| 古熊神社本殿 |
 |
本殿の正面にある三つの蟇股に、それぞれ松竹梅の彫刻が見られます。これは我が国で建築の装飾に松竹梅の組合せを取り入れた最も時代の古いものとして有名です。本殿は大正6年(1917)に国の重要文化財に指定されています。 |
| 古熊神社本殿 |
| 古熊神社の拝殿は桁行1間、梁間1間の楼門式建物で、屋根は入母屋造り、銅板葺きです。左右に翼廊(よくろう)があり、桁行1間、梁間2間で、屋根は切妻となっています。正面には1間の向拝がついています。 |
 |
| 古熊神社拝殿 |
 |
この楼門は下方が通路になっておらず、翼廊とともに全面に床が張ってあって、拝殿と同様な役目をしています。山口市内にある今八幡宮楼門と同様の形式で「楼拝殿造り」です。拝殿は昭和24年(1949)に国の重要文化財に指定されています。 |
| 古熊神社拝殿 |
洞春寺
とうしゅんじ
山口県山口市水の上町5ー27
Tel 083-922-1028

 |
正宗山(しょうしゅうざん)洞春寺は臨済宗建仁寺派のお寺です。明治元年(1868)萩城内から移した毛利元就の菩提寺です。応永11年(1404)大内盛見(もりはる)が祈願所として建立した国清寺が前身です。 |
| 毛利氏が防長に移ってからは、毛利隆元の菩提寺となりましたが、後に元就の菩提寺となり洞春寺と称しました。どっしりとした四脚門の山門は国清寺創建当時のもので、国の重要文化財に指定されています。 |
 |
 |
元の洞春寺は元亀3年(1572)、毛利輝元が祖父の元就の菩提寺として安芸吉田の城内に開基し、開山僧は嘯岳鼎虎(しょうがくていこ)禅師でした。慶長8年(1564)に毛利に従って山口に、次いで慶長11年(1567)に萩城内に移り、幕末に再び山口に移ったのでした。 |
| 現在の洞春寺本堂は、江戸時代に焼失して再建されたものです。洞春寺観音堂は上宇野令滝の観音寺にあったもので、国の重要文化財に指定されています。観音寺は大内義弘の子持盛の菩提寺で、後に勝音寺となり、毛利氏の時代になってからは大通院と称していました。大正4年(1915)に洞春寺に移築されたものです。 |
 |
 |
観音堂は桁行3間、梁間3間、1重もこし附入母屋造りの建物で、永享2年(1430)建立ということが厨子裏の板銘から判明したそうです。花頭窓や桟唐戸などが美しい唐様の建物です。 |
木戸神社
きどじんじゃ
山口県山口市糸米2

 |
木戸神社は吉田松陰のもとで学んだ木戸孝允(桂小五郎)を祀った神社です。孝允は萩に生まれ、幕末には新生日本のために活躍しました。薩長連合を図って明治新政府を樹立させ、内閣顧問を初め多くの要職について内外の政務に参与しました。明治10年(1877)に京都で病没しました。45歳の人生でした。 |
| 孝允は死を前にこの地にあった本宅山林などを地区民に与えて子弟育英の資とするよう言い残しました。 人々は大変感謝し、孝允旧宅の地に祠を建立し、明治19年(1886)には孝允を讃える「木戸公恩徳碑」を建てました。この祠を中心として木戸神社が創建され孝允の霊を祀ったのです。 |
 |
山口サビエル記念聖堂
山口県山口市亀山町4−1B
Tel 083-920-1549

 |
山口サビエル記念聖堂は、昭和27年(1952)にフランシスコ・サビエルが山口を訪れてから400年になるのを記念して建てられた聖堂です。 |
| ステンドグラスの美しかった聖堂は平成3年(1991)に焼失してしまいました。。平成10年(1998)に高さ53mの2本の塔が印象的な白亜の新聖堂が完成しました。 |
 |
 |
サビエルは大内義隆を頼り、天文20年(1551)に山口に2ヶ月滞在して布教活動をしました。その時に500名に洗礼を施したそうです。 |
| ザビエルの生家のあったスペインのナバラ州パンプローナ市と山口市は姉妹都市提携を結んでいます。 |
 |
常栄寺
じょうえいじ
山口県山口市宮野下2001ー1
Tel 083-922-2272

 |
常栄寺は臨済宗東福寺派のお寺です。常栄寺の庭園は、雪舟庭(せっしゅうてい)といわれる国の史跡、名勝です。 |
| 康正元年(1455)、大内29代大内政弘(まさひろ)が夫人(妙喜寺殿宗岡妙正大姉)の菩提寺妙喜寺(みょうきじ)の庭として、雪舟につくらせたものといわれています。 |
 |
 |
毛利氏が防長に移された後、妙喜寺は毛利隆元の夫人(妙寿大姉)の菩提寺となり、妙寿寺となりました。 |
| 幕末の文久3年(1863)、現在の洞春寺のところにあった毛利隆元の菩提寺、常栄寺がここに移り、常栄寺となりました。 |
 |
 |
本堂北面に広がる庭園は東西北の三方を囲む竹林などを借景にして、手前に心字池を設け、池の周囲に立石を配した池泉回遊式庭園です。 |
| 無数の石で中国にある西湖の風景を表現しているようです。 庭の東北側の隅には滝を設け、水と石で室町時代の代表的な庭園を造りあげています。 |
 |
宗隣寺
そうりんじ
山口県宇部市小串210
Tel 0836-21-1087

 |
宗隣寺は宝亀8年(777)、唐より来朝した為光(威光)和尚が松江山普済寺として創建しました。永和5年(1379)普済寺に寄贈された重要文化財の朝鮮鐘(大阪鶴満寺所蔵)に「宇部郷松江山普済禅寺」の追銘のあることから確かなことです。その後寛文10年(1670)宇部領主の福原氏15代広俊が宗隣寺として再興したそうです。 |
| 本堂の北側にある「龍心庭」は南北朝時代に造られた山口県最古の庭園です。岩手県の毛越寺と宗隣寺にのみ現存する干潟様と称する古庭園の方式で、水の増減により二段池が見え隠れする手法です。 |
 |
 |
須弥山式禅宗庭園で奇岩巨岩を用いず池の中に二列直線八石夜泊石を配しただけの禅の真髄を説いている作風です。国の名勝庭園に指定されています。 |
| 背後の山には長州藩家老で宇部の領主・福原氏歴代の墓があります。幕末の蛤御門の変に敗れ、責任をとって切腹した福原越後の一際大きな墓があります。 |
 |
赤間神宮
あかまじんぐう
山口県下関市阿弥陀寺町4ー1

 |
赤間神宮は文治元年(1185)、源平合戦の最後、わずか8歳で壇ノ浦で沈んだ安徳天皇を祭った神社です。 |
| 江戸時代までは真言宗のお寺で聖衆山阿弥陀寺というお寺だったそうです。阿弥陀寺町といまでも地名には残っています。 |
 |
 |
明治の神仏分離により阿弥陀寺は廃され、神社となって「天皇社赤間宮」と改称されました。昭和15年(1940)官幣大社に昇格し赤間神宮となったのです。 |
| 文治元年(1185)の壇ノ浦の戦いで入水した安徳天皇の遺体は御裳川で引き上げられ、阿弥陀寺境内に埋葬されました。 |
 |
 |
建久2年(1191)、勅命により御陵に御影堂が建立されたそうです。以後、勅願寺として崇敬を受けました。 |
| 安徳天皇の命日は壇ノ浦合戦のあった3月24日ですが、赤間神宮が神社として成立した明治8年(1875)に新暦に換算されました。以来5月2日を安徳天皇命日として、毎年3日間追悼祭典が行なわれています。 |
 |
 |
第二次大戦により社殿を焼失し、昭和40年(1965)新社殿が再建され現在に至っています。 |
| 高浜虚子の「七盛の墓包み降る椎の露」という句が境内に残されています。 |
 |
 |
境内には安徳天皇陵があるほか、七盛塚と呼ばれる平家一門の墓があります。源平壇之浦の合戦で平家が滅亡して以来、関門海峡で海難事故が頻発し、平家の怨霊が騒ぎ出したためと恐れられていました。 |
| 下関近辺に散在していた平家の墓標をこの地に集約して1600年ごろに建てられた、平家一門の供養碑なのです。 |
 |
 |
また境内には芳一堂があります。 「耳なし芳一」を祀り、芳一の木像を安置しています。小泉八雲ラフカディオハーン怪談「耳なし芳一」で有名になりました。 |
功山寺
こうざんじ
山口県下関市長府川端1ー2ー3

 |
金山功山寺は元応2年(1320)に創建された曹洞宗のお寺です。国宝に指定されている仏殿は嘉暦2年(1320)に建てられた鎌倉期のもので、わが国最古の唐様禅宗式建築です。 |
| 礎石と柱の間には木製の基盤が入り上下部分が細くなるちまき形の柱です。花頭窓と呼ばれる特殊な窓もあります。 |
 |
 |
功山寺は当初は臨済宗で金山長福寺というお寺でした。足利氏、厚東氏などによって保護され、大内氏が周防、長門を統一するとますます篤く保護されました。 |
| 弘治3年(1557)主君であった大内義隆を攻め滅ぼした陶晴賢は、大友義鎮(宗麟)の弟晴英を大内義長と改名させ大内家の当主にさせました。厳島で晴賢を破った毛利元就は、義長を攻めました。 |
 |
 |
敗れた義長は、わずかな近従と長福寺に入り、自刃したのでした。6歳になる陶晴賢の末子鶴寿丸も義長とともに果てたのでした。 |
| 慶長7年(1602)長府5万石の藩祖として入封した毛利秀元(元就の孫になります)が荒廃した堂宇を修営しました。その時に曹洞宗に転宗したそうです。 |
 |
 |
二代藩主光広が、秀元の霊位をこの寺に安置し、長府毛利家の菩提寺となりました。慶安33年(1650)秀元の法号の智門寺殿功山玄誉大居士にちなんで功山寺と改められました。 |
| 文久3年(1863)の政変で都を追われた討幕派の三条実美はじめ5人の公卿が功山寺にひそんでいました。奇兵隊の結成させたことで有名な高杉晋作は藩論回復のため、遊撃隊士などわずか80人ばかりの同志をひきいてこの功山寺で決起したのです。 |
 |
 |
晋作は私兵でない証とするため、匿われていた5人の公卿にあいさつしたのち挙兵しました。次々と同士が集まり、ついには討幕の藩論を確定させたのでした。 |
日清講和記念館
にっしんこうわきねんかん
山口県下関市阿弥陀寺町4−2
TEL 083-223-7181

 |
明治28年(1895)4月17日、日清講和記念館は日清戦争の講和会議が開かれた旅館春帆楼(しゅんぱんろう)の敷地内にあります。 |
| 日本の全権は伊藤博文、陸奥宗光、清国の全権は李鴻章、李径方でした。日清講和条約を締結した際のテーブル、椅子、調度類や資料が、当時のままに再現されています。 |
 |
 |
春帆楼は老舗の割烹旅館です。明治21年(1888)、内閣総理大臣だった伊藤博文が春帆楼でフグ料理を食べました。豊臣時代以降フグ料理は禁制品でした。ご禁制が解かれ、フグ料理公許第1号となったところでもあるのです。 |
| 朝鮮半島の権益をめぐり対立していた日本と清国は、明治27年(1894)東学党の乱をきっかけに開戦しました。この戦争は日清戦争と呼ばれ、戦況は日本軍の圧倒的優勢に進み、翌年
清国は日本に講和の打診を始めました。 |
 |
 |
李鴻章が小山という青年に狙撃され、負傷し会議は一時中断しましたが4月17日に講和条約が調印されたのです。この講和条約は「下関条約」と呼ばれ、清国は日本に朝鮮半島の独立承認、領土の割譲、賠償金の支払いなどを約束しました。 |
旧下関英国領事館
山口県下関市唐戸町4−11
Tel 083-231-1238

 |
明治34年(1901)9月、英国領事館が下関に設置されました。これは時の駐日英国大使で長州と連合国との戦争で通訳をしたアーネスト・サトウの強い推挙が実を結んだ結果でした。明治39年(1906)、領事業務の拡大に伴い、領事館が新たに建設されました。これが現在の建物です。国の重要文化財に指定されました。 |
藤原義江記念館
ふじわらよしえきねんかん
山口県下関市阿弥陀寺町3−14
TEL 083-234-4015

 |
藤原義江記念館は昭和11年(1936)に建てられた旧リンガー邸を使っています。英国系商社ホーム・リンガー商会の社長令息のために建てられた住宅でした。リンガー商会の支配人であったスコットランド人のネール・ブロディ・リードと琵琶芸者であった坂田キクとの間にできたのが義江でした。 |
| 藤原義江(1898-1976)は日本にオペラの基礎を創りあげた世界的オペラ歌手でした。幼少の頃、父からは認知されず、母と共に各地を転々とする苦しい時代を送ったようです。 |
 |
毛利家墓所(長府毛利累代墓)
もうりけぼしょ(ちょうふもうりるいだいのはか)
山口県下関市長府川端1ー2ー3
Tel 0832-45-0258

 |
毛利家墓所は長府功山寺の仏殿裏手にあります。初代長府藩主である毛利秀元を始め、9人の藩主達の墓があります。 |
| 毛利秀元は元就の孫で、秀吉の朝鮮出兵において武将として高く評価された武将でした。関が原の戦い後、毛利氏の削封に際して長府藩を創設、城下町としての基礎を築きました。 |
 |
 |
慶長7年(1602)毛利秀元は荒廃した功山寺の堂宇を修営しました。二代藩主光広が、秀元の霊位をこの寺に安置し、長府毛利家の菩提寺となりました。慶安3年(1650)秀元の法号の智門寺殿功山玄誉大居士にちなんで功山寺と改められました。 |
 旅と歴史のホームページへもどる 旅と歴史のホームページへもどる  日本のページへもどる 日本のページへもどる
|
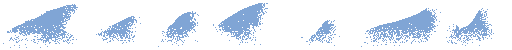

 旅と歴史のホームページへもどる
旅と歴史のホームページへもどる  日本のページへもどる
日本のページへもどる 




